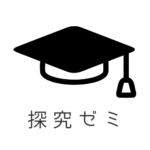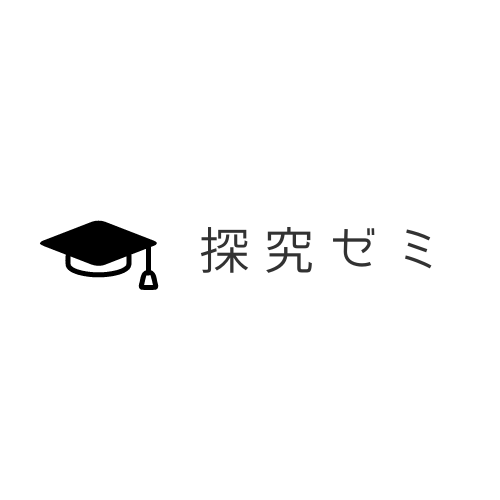第2回:自動収穫ロボットの核心は“取る動作” ─ 「わからない」を「わかる」に変えるAI農業ベンチャーinahoの挑戦

菱木 豊(ひしき・ゆたか)
株式会社inaho 代表取締役。不動産・IT分野での事業経験を経て、2017年に株式会社inahoを創業。AIを活用した「自動収穫ロボット」を自社開発し、RaaSモデルでサービスを提供。持続可能な農業の実現を目指し、国内外で事業を展開。
目次
電話は苦手でメールで営業
ーー大学教授など研究者に営業する時、どのような方法でアプローチしたのですか?
研究者へのアプローチについては、僕は正直電話で断られるのが苦手なので、すべてメールで連絡していました。
ただ、5件や10件ではなく実際には100件以上送ったんです。そうやって数をこなすことで、ようやくいくつか返事をいただける、そういう世界です。
営業先の選び方は、そのときはロボットを作れる方を探していたので、研究内容を確認して、ロボット関連の研究をしている先生をスクリーニングしていました。
*スクリーニング:数多くの専門家のなかから条件に見合った方を選び出すこと

ロボット開発の肝は「取る」動き
ーー大学の先生方と共同開発する中で、最初はどのような技術に取り組まれたのですか?
AIを使って画像処理をするところまではイメージできていました。ただ、実際にロボットとして実装するには要素を細かく分ける必要がありました。
先生方に相談する中で、足回りの「動く」動作が得意な先生、ハンド部分の「取る」動作が得意な先生など、分担が見えてきました。
足回りはいろんな動きが比較的簡単にできる一方で、ロボットの核になるのは「取る」動作です。マニピュレーターと呼ばれるその部分が非常に重要だとわかり、そこに強みを持つ先生に絞って進めていきました。
*マニピュレーター:人間の腕を模倣した構造を持つ、ロボットの一部。主に産業用ロボットにおいて、物体を掴んだり、移動させたりするために使用される。
「前に進むだけ」の動作なら制御も単純ですが、「取る」動作は制御すべき部分が格段に多いんです。
維持する部分、手先の部分など複数の要素を同時にコントロールする必要があります。複雑性が一気に増して、難易度が高くなります。
「儲かる」で人は集まらない
ーー人を集める上で大切にしていることは何でしょうか?
やはり「大義がある」「社会にとって必要である」テーマだと、多くの人が共感して動いてくれると感じます。逆に「自分が儲けるため」という文脈では、それほど人数は集まらないと思います。
採用媒体や自社のホームページ経由で連絡いただくこともありますが、本当に大きな人数が集まったのは、東日本大震災関係の合同イベントのときでした。
ボランティアだけで百何十人もの方が協力してくださり、私にとって初めての経験だったので、とても印象深かったです。
自分よりも世の中にとって
ーー現在の事業でもその考え方は活きていますか?
もちろんです。現在も「自分がこうしたい」より「世の中にとってこうあった方がいい」というビジョンをベースにしています。
農家さんが協力してくださるのも、社員が集まるのも、そのビジョンに共感してくださるからだと思います。
人によっては「儲かるから」や「みんなで年収を上げよう」でも十分なテーマになるでしょう。でも私の場合は「こうすれば課題を解決できるのでは」という筋道を示すことで、人が自然と集まってきました。
テーマ設定が何より大事だと思います。
資金面については、損益分岐点をどこに設定するかで考え方は変わってきます。単年で黒字を目指すのか、単月で考えるのか、それともこれまでの投資を何年で回収するのか。さまざまな角度から戦略を立てています。
資金調達も、エクイティや補助金など、複数の方法を組み合わせています。気候変動に対応するための保守費用や農機のコストも含めて、どう資金を循環させていくかが、これからの大きなテーマです。
気候変動と資金、二つの課題
ーー現在、事業で最も力を入れていることと、その課題について教えてください。
農業の難しさは、春夏秋冬で環境が大きく変化する点にあります。
工場なら環境を一定に保てますが、自然を相手にする農業ではそうはいきません。気候や野菜の成長に合わせて技術を調整する必要があり、その対応が大きなチャレンジになっています。
資金面でも課題はあります。潤沢に資金があるわけではなく、やればやるほど「次に挑戦したいこと」が増えていくため、調達や投資が欠かせません。
データで「わからない」を「わかる」に変える
ーー最近の新しい取り組みで面白かったことはありますか?
2025年の4月から、自分たちでも野菜の生産事業を始めました。
農業には「わからないことが当たり前」とされてきた部分が多くありますが、社内のエンジニアが新しい発想で「データとしてちゃんと取れる」仕組みを発明してくれるようになりました。
化学出身のメンバーが、農学研究者では考えにくい計画的アプローチで課題を解くなど、異分野の知恵を持ち寄れるのが面白いです。
必ずしも利益に直結するとは限りませんが、「もしできたらとんでもないことになる」という希望を支えに進めています。
事業成長を支える資金戦略
ーー資金調達に関して方針があれば教えてください。
資金面については、損益分岐点をどこに設定するかで考え方は変わってきます。単年で黒字を目指すのか、単月で考えるのか、それともこれまでの投資を何年で回収するのか。さまざまな角度から戦略を立てています。
資金調達も、エクイティや補助金など、複数の方法を組み合わせています。気候変動に対応するための保守費用や農機のコストも含めて、どう資金を循環させていくかが、これからの大きなテーマです。
【文:安村綾夏 / 編集:若林千紘】
投稿者プロフィール