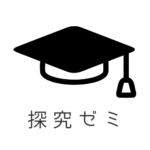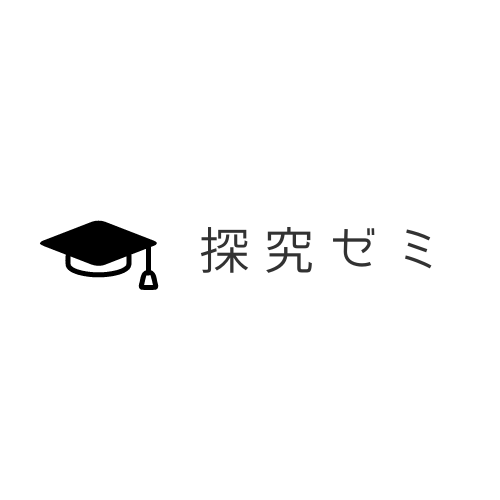第1回:AIで農業を変革する「自動収穫ロボット」:inaho菱木豊氏が語る、雑草取りから始まった創業とイノベーション

菱木 豊(ひしき・ゆたか)
株式会社inaho 代表取締役。不動産・IT分野での事業経験を経て、2017年に株式会社inahoを創業。AIを活用した「自動収穫ロボット」を自社開発し、RaaSモデルでサービスを提供。持続可能な農業の実現を目指し、国内外で事業を展開。
目次
AI×農業で起業したきっかけ
ーーinahoさんが2017年に創業された当時、農業界にどのような課題意識を持っていらっしゃいましたか?
農業現場での課題は、ものすごく労働集約的な作業が多く、人の手でしかできない作業が多くあることでした。それが原因で、売上利益を伸ばすために農地面積を大きくすることも出来ないのが現状でした。
そこで、AIやロボットというテクノロジーを活用して、それらを改善する何かができればいいなと思い、最初は雑草取りから始めました。
話してわかった農家の課題
ーーなぜAI×農業というポイントに目をつけられたのでしょうか?
僕自身、当時AIの勉強をしていて、今のAIはどういったことが出来るのか、これからどういうことが出来るようになるのかということをインプットしていました。
当時は農業界にどんな課題があるのかは知らなかったのですが、ある時現場の農家さんに「今世の中のAIはこういうことが出来るようになっています」と話をしたことがありました。
その時に、「じゃあAIの技術を使って、雑草を取るようなことができないか?」と問いかけられて、話をしていくうちに農業界の課題が分かっていきました。

画期的なAI技術の可能性
ーー 2017年当時、生成AIが一般的に話題になる前の段階で、AI技術の活用についてどのような可能性が考えられていましたか?
当時、「ディープラーニング」という技術ができたのですが、それはAI業界の中でもかなり画期的な技術開発でした。
ディープラーニングができて、世の中で知られるようになってから1年ぐらいのタイミング(2015年くらい)で、この技術について勉強する機会がありました。
当時は生成AIとかも全く無かったのですが、ディープラーニングという、人の目に変わるような画像処理ができるようになったのがその頃でした。
*ディープラーニング:人間が手を加えなくても、コンピュータが自動的に大量のデータからそのデータの特徴を発見する技術のこと。
ーー AIを活用できる分野が多岐にわたる中で、なぜそれを農業分野で活かそうと思われたのですか?
それまで農業界ではAIが使われていなかったからこそ、新たにその技術を活かす意味があると思っていました。
例えば、当時からあった農機具メーカーのクボタさんやヤンマーさんは、トラクターやコンバインなどの、区外で働く大きな農機をやっていました。
しかし我々が今やっているような、ハウスの中で動くものはあまり力を入れて取り組まれていないなと思っていて。
それらをやる人材も少なかったというのもあり、十分社会的にやる意義があると感じていました。
留学×中退×専門学校
ーー学生時代は調理学校に通われていたと伺いましたが、その頃の経歴について教えてください。
高校卒業後は大学に入って、大学1年の夏から約1年間、アメリカに留学をしたんです。その後日本に戻ってきて大学を辞め、21歳で調理の専門学校に入りました。
大学に入ったときは、何か将来やりたいことがあったというわけではないんです。今もそういう学生は多いと思いますが、自分もその一員でした。
そこでアメリカに留学に行って、友達にご飯を作って振舞ったときに、ものすごく感謝されて。その時に「こんなに人に感謝されることって嬉しいんだ」と感じました。
具体的な料理は覚えていませんが、日本の家庭料理を振舞いました。海外の人ではなく日本人に振舞ったのですが、みんな日本食を恋しく思っていたのもあり、すごく感謝されました。
その経験がきっかけで、何となく大学生活を過ごすよりも、何か人に喜ばれることをやろうと思い調理学校に入りました。
社会のために、チームで動く
ーー料理の道に進まれた後、起業に至るまでに心境の変化はありましたか?
僕が起業したのは、今の会社が3社目なんです。1社目は1人で、2社目は2~3人でみたいなところから、 現在はスタートアップをやっています。
法人ではありましたが、あまり面白くありませんでした。売り上げを立てると直接自分の収入になるわけなんですが、嬉しくなくて。
自分1人だけで目標達成するのではなくて、みんなと共有したい、何人かでやりたいという思いで始めました。
やはりチームでやるのが面白いなと感じて、そのときはウェブサービスやイベントをやっていました。やるからにはただ楽しくやるだけより、社会的意義といったところに注ぎたいと思いました。
誰もやっていないことができると価値あるよね、と思って今のスピードを選んでいきました。
1番最初の関係構築は泥臭く
ーー 起業するにあたって、どのように農家さんとの関わりを築きましたか?
一番最初は、AIの画像認識等ができる研究者の方が知り合いにいたので、野菜と雑草の写真を見てもらって、「AIでこれの判別できますかね?」などと相談したりしていました。
ロボットに関しては、そういった知り合いは特にいなかったので、色々な大学に連絡させていただいて、その大学の先生にお手伝いしていただくという形でした。
あとは、イベントで繋がることもありますし、ホームページを持っている人に連絡することもあります。
ホームページを持っている人はほぼいないので、その人がWebメディアに取り上げられていたら、そのWebメディア会社に連絡します。
「こういうことを相談したいから、ちょっと繋いでくれないか」と伝えていただいたり、ハローワークに出ている求人情報の電話番号を調べて直接電話してみるとか。
SNSがない場合があるので、繋がれるところは頑張って繋がるみたいな、スーパー泥臭いことをやっていました。
農家さんはウェルカムだった
ーー農業にAIを取り入れるとなったとき、農家さんから批判的な目で見られることはなかったのでしょうか?
我々の場合は、ものすごくウェルカムな感じでした。なぜなら、単純に農業における課題がものすごく重大なものだったからです。
自分ごととして「何とかしてくれ」と思っている人達が大多数だったので、お願いすると基本的に全振りで協力してくれるという感じでした。
【文:市川理紗子 / 編集:相木大空】
投稿者プロフィール